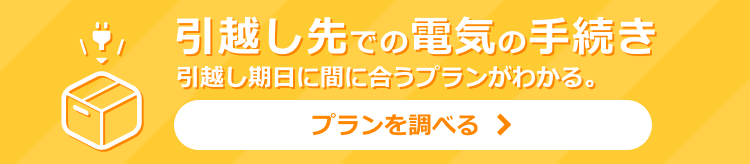帝王切開、気になる費用の平均は?お役立ち情報もご紹介!

赤ちゃんが生まれるとき、場合によっては帝王切開を行うことがあります。さて、帝王切開をすることになった場合、費用は平均してどのくらいかかるのでしょうか?知っておきたいお役立ち情報と合わせてご紹介します。
年間平均32,588円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2024年1月1日~2024年3月31日)
帝王切開、いくらかかる?
最低限これだけは用意しよう!
と、いうことで最低限用意したい金額を、平均額から考えてみましょう!帝王切開の費用は、普通分娩の費用に帝王切開の処置にかかる費用を足すことで求められます。
普通分娩の費用の平均は486,376円(平成26年)。約49万円です。そして、帝王切開にかかる費用は約6万円(※診療報酬点20,140点、診療報酬点1点=10円、3割負担として計算した場合、自己負担分は60,420円)。
つまり、平均55万円前後。最低限これぐらい用意しておけばいいかもしれません。
健康保険がきく?
お金のことについて、ぜひ押さえておきたい知識をお伝えします。出産は病気ではないので、健康保険が適用されないことを知っている人は多いかもしれません。しかし、帝王切開になった場合は、健康保険上では病気として扱われるため、健康保険が適用されます。つまり、自己負担分が大幅に減るのです。
それでも普通分娩よりお金がかかる理由
健康保険が適用されるとなると、自己負担分は大幅に減ります。しかし、普通分娩よりお金がかかるということも……なぜでしょうか?帝王切開を行ったとしても、健康保険がきく=自己負担分が少なくて済むのは、帝王切開に関わる費用の部分だけです。その他の自己負担分、保険外診療費用(食事料、分娩介助料、検査料、その他雑費)については全額自己負担になります。
また、普通分娩なら入院期間は短くて4~5日、長くても1週間程度。しかし、帝王切開の場合は短くて1週間、長いと10日以上になります。その分、自己負担分が増えてしまうのです。また、お腹を切り開くことになるため、退院後のケアにも時間とお金がかかります。そのあたりもよく考えて備えをする必要があるでしょう。
高額療養費制度をうまく使おう

わかりやすく言えば、一か月に出した医療費が一定額を超えた場合、超えた部分については払わなくていい制度のことです。
前に書いた通り、帝王切開は健康保険上では病気として扱われます。そのため、この制度が使えるのです。制度を使うには、事前に手続きをする方法と、事後に手続きをする方法があります。あらかじめ帝王切開をすることがわかっているなら、事前に手続きを進めたほうがいいかもしれません。具体的な手続き方法は、加入している健康保険組合に問い合わせましょう。
帝王切開はどんな時に行う?
事前にわかっている場合
以下のような場合は、事前に帝王切開をすることがわかります。
- 巨大児・胎児機能不全
- 赤ちゃんが大きすぎる、または小さすぎる、ということです。母子ともに危険が及ぶことがあるため、帝王切開を行うことが多いです。
- 前置胎盤
- 胎盤の一部または全部が子宮口をふさいでいることがあります。この場合、普通分娩では出産が困難です。
- 児頭骨盤不均衡(CPD)
- お母さんの骨盤と赤ちゃんの頭のサイズが合わない場合をいいます。この場合も、普通分娩では出産が困難です。
- 多胎妊娠
- 赤ちゃんが双子、もしくはそれ以上の場合です。最近では帝王切開を行うことが多いです。
- 感染症
- お母さんがヘルペス、HIVなどのウィルスに感染している場合、赤ちゃんへの感染を防ぐため帝王切開を行います。
なお、手術の時期ですが、お母さんと赤ちゃんに危険が及びにくい妊娠38週前後になることが多いようです。
その場の判断で行う場合
普通分娩によるお産が始まった場合でも、途中で帝王切開に切り替える、ということは珍しくありません。具体的には、以下のようなケースに帝王切開への切り替えが行われます。
- 赤ちゃんに危険が及ぶ場合
- 心拍、呼吸の異常などが起こっている。
- お母さんに危険が及ぶ場合
- アナフィラキシーショック、脳出血などを起こす可能性がある。
医師は赤ちゃんとお母さんの様子を見て、母子ともに無事に出産を終えるための判断をします。いざそうなったら慌てるかもしれませんが、医師を信頼してお任せしましょう。
事前にわかっている場合は準備しよう
となると、事前に帝王切開をするとわかっているときは、準備をきっちりすれば不安は和らぐはず。次のポイントをしっかり押さえてください。
- 最低でも55万円は用意すること。
- 高額医療費制度を活用すること。
- わからないことは調べること。
お母さんがリラックスして出産を迎えるため、ベストをつくすことを心がけましょう!