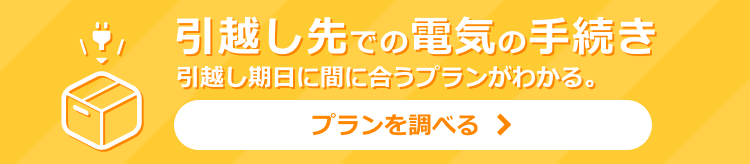美容室開業にはいくらかかる?資金調達についても解説します!

この記事の目次
美容室を開業したい、サロンオーナーになりたい美容師の人、いませんか?夢の実現に向けて動くのはいいことですが、ちゃんと計画を立てないと、あとあと大変です。今回は美容室の開業資金について、「いくらかかるのか」「お金はどうやって集めればいいのか」を徹底解説します。いつかサロンオーナーを目指す人は、いい機会なので勉強してください。
年間平均32,588円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2024年1月1日~2024年3月31日)
実際、美容室を開業するにはいくらかかる?
内訳をまとめてみました
ということで、かかる費目と金額の一例をまとめてみました。もちろん。工夫次第ではもっと下げることも可能ですが、美容室を開業するにはそれなりに資金が必要だ、ということがお分かりいただけるかと思います。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 敷金 | 30万円 | 家賃1か月分 |
| 店舗礼金 | 30万円 | 家賃1か月分 |
| 店舗仲介手数料 | 30万円 | 家賃1か月分 |
| 家賃 | 360万円 | 家賃1年分 |
| 火災保険料 | 5万円 | |
| 保証会社手数料 | 30万円 | 家賃1か月分 |
| 内外装工事費 | 700万円 | 店舗デザイン、工事費用 |
| 美容器具 | 150万円 | セット椅子、シャンプー台等 |
| その他設備 | 75万円 | パソコン、洗濯機、乾燥機等 |
| 開業材料費 | 50万円 | シャンプー剤、カラーリング剤等 |
| 広告宣伝費 | 50万円 | ショップカード、チラシ、HP作成、ポータルサイト掲載料 |
| 人材採用費 | 50万円 | 求人広告誌出稿費用、研修時の時給その他 |
| その他諸経費 | 40万円 | 雑誌、観葉植物、インテリア雑貨等 |
| 運転資金 | 400万円 | 当面の美容室運営のために残しておく費用 |
| 合計 | 2,000万円 |
あくまでこの金額は一例にすぎません。しかし、相当な覚悟をもって臨まなければいけない話ではあるようです。
資金はどう調達する?

さて、ここまで莫大な資金がかかるとなると、どう調達するかを考えなくてはいけません。繰り返しになってしまうかもしれませんが、どんなに頑張って今まで働いて、開業資金を貯めてきたとしても、必要な資金を全部賄うのは、なかなか厳しいもの。そこで「誰か(どこか)から借りる=融資を受ける」という選択肢が浮かび上がります。でも、どうすればいいのでしょうか?
銀行からは無理
具体的な話より前に、大前提として覚えておいてほしいことがあります。融資を受ける、というと、多くの人が「銀行に相談すればいいんじゃない?」と思うでしょう。しかし、独立開業したての人に融資をしてくれる銀行はほとんどないです。これは、銀行の融資にあたっては決算書など、これまでの業績を示す書類が必要である場合が多いためです。これから独立開業という場合、これまでの業績はないのが普通。銀行の融資が過去の業績に基づき、信用力を審査し行われるという性質がある以上、独立開業の資金調達手段としてはあまり使えそうにありません。
資金調達を考えるプロセス
銀行からの融資にはあまり期待できないとしたら、どうやって資金調達をすればいいのでしょう?次の4つの手順を試してみてください。
- 必要資金を計算し、自分でどこまで用意できるか考える。
- 助成金、補助金が使えないかチェックする。
- 2までのプロセスを踏まえ、公的機関からの融資が受けられないか検討する。
- 3までやっても足りない場合、スポンサーとなってくれる人物を探す。
どんな補助金が使える?
創業促進補助金
この補助金は、新しい産業の創設・雇用を通じ、地域の活性化に貢献しようとする人を支援することを目的としています。毎年募集していますが、募集の都度細かい条件は変わる可能性があるので注意してください。
採用されれば、店舗・設備の賃貸費用、マーケティングのための経費、広告費、人件費、専門家への顧問料などに使える補助金が最大200万円まで支給されます。ただし、補助額が100万円に満たない場合、対象外となりますので注意しましょう。
なお、補助金は後払いです。つまり、補助の対象となる事業を行い(ここでは、美容室の経営)、報告書等の被必要書類を提出し、検査を経て合格すれば初めて補助金を受け取ることができるのです。手続きにもれがあるともらえない可能性も高いです。確実にもらいたいなら、税理士等専門家のアドバイスを仰いだほうがいいかもしれません。
その他、細かい規定については、公式ホームページをご参照ください。
公的機関からお金を借りるには?

補助金を受けても、まだまだ資金が足りない!ということもありうるでしょう。そういうときに検討してほしいのが、公的機関からの融資です。公的機関からの融資には、大きく分けて地方自治体が行う制度融資と、政府の管轄下にある日本政策金融公庫が行う融資があります。この2つの融資の概要について、説明します。
制度融資(地方自治体)
地方自治体が信用保証協会と連携し、中小企業を支援する目的で、独自の基準で行っている融資です。つまり、地方自治体によって、まったく融資の条件等が異なります。
また、どの地方自治体でも、必ず求められる条件は次の2つです
- 中小企業者であること
- 信用保証協会の対象業種であること
具体的に、どのような条件で融資を受けられるかは、開業しようとする地域を管轄する役所に相談することをおすすめします。なお、どの地域であっても、制度融資を受けるまでは、次のような流れを経て手続きが進行します。
- 自治体の窓口に相談に行く。
- 自治体に融資あっせんの申し込みを行う。
- 自治体から紹介状を発行してもらう。
- 紹介状を持って、金融機関に行き、融資を申し込む。
- 金融機関の審査(=面談)を受ける。
- 信用保証協会に信用保証の申し込みを行う。
- 信用保証協会の審査(=面談)を受ける。
- 信用保証が実行される。
- 融資が実行される。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は国が株式の全部を保有している、政府系の金融機関です。中小企業向けに、様々な支援サービスを提供しています。中小企業の新規創業にも積極的な支援を設けているのが特徴です。そのため、過去の実績がない場合でも比較的融資が受けやすいといえます。その他にも、次のような特徴があります。
- 無担保、無保証制度
- 多額の資金を調達するとき、担保の提供または保証人の指定が求められることは少なくありません。しかし、担保も保証人も用意できないこともあるでしょう。日本政策金融公庫の「第三者保証人等を不要とする融資」を用いれば、担保も保証人も不要です。
- 金利が低い
- 民間の金融機関で融資を受けた場合、会社の業績がよければよいほど、低い金利となります。言い換えれば、逆もありうるということです。この点、日本政策金融公庫では心配いりません。融資の種類によって、金利はきっちり決まっています。つまり、審査に通れば、財務内容にかかわらず一律の金利が適用されるのです。
- 固定金利
- 日本政策金融公庫の融資は、固定金利が原則です。つまり、返済が終わるまで、ずっと同じ金利で借りられるということ。そのため、中長期の事業計画、資金繰り計画が立てやすいというメリットがあります
- 借入期間が長い
- 民間の金融機関の場合、事業資金の融資期間は短いです。最短で半年、長くても数年で返済するのが一般的となっています。これに対し、日本政策金融公庫の場合は最長で20年に設定されています。長いスパンで返済計画を立てられるので便利です。