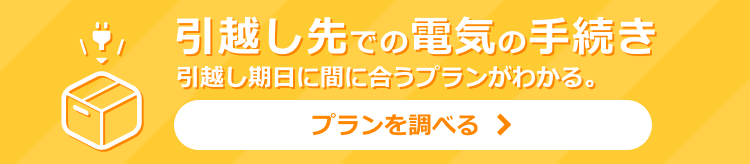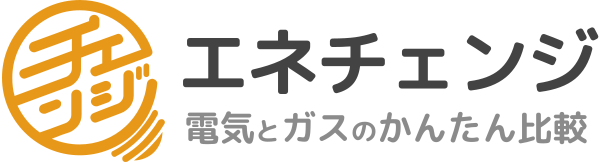家計における保険料の割合はどの位?【夫婦+子ども編】

この記事の目次
いったいいくら、保険にお金をつぎ込めばいいのか。家計全体のうちの保険にしめる割合は、どの家庭でも大きなテーマとなってきます。安すぎても不安だし、高すぎたら払えないし。そこで、「みんなの保険料事情」と、保険選びで知っておきたいポイントをまとめてみました。
年間平均21,939円節約できます!
エネチェンジ電力比較診断の3人世帯を選択したシミュレーション結果で、電気代節約額1位に表示されたプランの年間節約額の平均値です。節約額はギフト券などの特典金額も含まれています(シミュレーション期間/2022年5月1日〜2022年6月12日)
実際、みんなどれぐらい払っている?

家計の6%くらいです
公共財団法人生命保険センターが平成24年に行った調査によれば、保険料の支払額の平均は「1世帯あたり、年間で約41万6,000円」だそうです。これは、家計の6%程度にあたるとか。生命保険を契約するときの大体の目安にしておきましょう。
出典:公益財団法人生命保険文化センター「生命保険の保険料は年間どれぐらい払っている?」
参照:アクサダイレクト生命「ハピスマ大学 第10回 家計費の理想割合を意識する」
高すぎても安すぎてもダメ
一体いくら保険料を払えばいいのかは、人によって違いがあります。充実した保障を望むなら当然高くなりますし、そこそこの保障でいいなら安く済ませることもできます。ただし、あまりに保険料が高すぎると、払い続けられなくなった場合問題です。あとでも書きますが、保険商品によっては、払い込んだ保険料が全部戻ってこないこともあります。
となると、「じゃ、保険料は安くしておこうかな……」と考えてしまうかもしれません。でも、保険料を安くしすぎても、いざというときに必要な保障が受けられない可能性が出てきます。つまり、保険料をいくら払うべきか?というのは非常にデリケートな問題です。保険は、長い間、安くないお金をを払い続けるもの。そう考えると、保険って、結構高い買い物なんです!くれぐれも、慎重に考えましょう。
保険を選ぶコツを教えて!
ご主人(=夫)のための保険
ご主人(=夫)が家計を主に担っている場合、考えなくてはいけないのは次の3つです。
- 入院時の治療費
日本の健康保険に入っている人ならば、1月あたりの医療費が一定額を上回った場合、上回った部分については戻ってくる、という制度があります(高額医療費制度)。とはいえ、一時的に立て替えて支払わなければいけないのは確かです。やっぱり、ある程度の備えは欲しいところ。
もし、家族や親戚に特定の病気(例:ガン、心臓病)にかかっている人が多い場合は、その病気に対し手厚く保障してくれる商品を選ぶといいかもしれません。また、健康保険でカバーできない治療(いわゆる「先進医療」)を望む場合、この費用をカバーしてくれる契約を結ぶ必要があります(先進医療特約)。
参照:厚生労働省「先進医療の概要について」- 入院、療養時の生活費
- 病院でかかる治療費と違い、こちらは健康保険が利きません。入院していても家族の生活費はかかります。また、退院してもすぐに仕事に復帰できるとは限りません。家族が生活に困らないように、ある程度の備えは必要でしょう。
- 死亡保険金
- 万が一、奥様(=妻)とお子さんを遺していってしまうことになった場合のことも考えておかなければいけません。奥様とお子さんの年齢にもよりますが、ある程度まとまったお金がないと困るのも事実です。当然、遺したい金額が大きいなら保険料は高くなるもの。「自分がいなくなってしまった場合、これだけは遺してあげたい」という最低限のラインを決め、そこから保険料を割り出すことが必要です。
奥様(=妻)のための保険
奥様(=妻)の保険についても、考えなくてはいけない問題があります。基本的にはご主人の保険と同じですが、これに加え、奥様が病気やケガで療養する場合を考えてください。そうなると、誰がお子さんの面倒をみるのか?という問題がのしかかってきます。
ご主人が介護休暇を使える、家族に頼める、というなら話は別です。でも、現実はそうもいかない場合も多いでしょう。このとき、ベビーシッターや保育園を用いてお子さんの面倒を見てもらう出てくるかもしれません。お子さんが小さいうちは、このような費用も見据えた保険選びも大事になってきます。
最低限知っておきたい保険用語

保険期間
「病気やケガをしたとき、万が一のことがあったときにお金(=保険金)をもらえる期間」のことです。パンフレットに「保険期間:終身」と書かれていた場合、亡くなるまで保険金はもらえます。
保険料払込期間
「月々の保険料をいつまで支払わなければならないか」ということです。パンフレットに「保険料払込期間:満60歳」と書かれていた場合、60歳になって初めて迎える毎年の契約日まで保険料を払うことになります。
なお、保険期間と保険料払込期間は、毎月払う保険料=月払保険料と密接に関係しています。関係を表にしてみました。
| 期間を延ばす | 期間を短縮する | |
|---|---|---|
| 保険期間 | 月払保険料は上がる | 月払保険料は下がる |
| 保険料払込期間 | 月払保険料は下がる | 月払保険料は上がる |
解約返戻率
保険を契約するときに知っておいてほしいことがあります。何らかの理由で、途中で保険を解約する場合、払い込んだ保険料が全額戻ってくるとは限りません。保険商品によって異なりますが、契約をしてから一定の年数が経っていないと、払い込んだ保険料が戻ってくる割合がとても少ない場合があるのです。
ここで注目してほしいのが、解約返戻率です。わかりやすく言えば、「払い込んだ保険料の何%が戻ってくるか?」という数値と考えてください。100%を超えていれば、解約しても払い込んだ保険料の分以上は戻ってくる計算になります。保険を契約するとき、見直すときの参考にしましょう。基本的にどの保険会社で相談しても、解約返戻率に関する説明書類を作ってくれます。
夫婦の保険の割合に関するまとめ
- 自分が何を保険に望むのか明らかにする。
- わからない、納得しないことを残したまま契約しない。
となると……やっぱり、専門家に相談してみましょう!最近では、様々な会社の保険商品を比較して選べるカウンターも増えてきました。気軽に相談しに行ってみましょう。
参照:ほけんの窓口