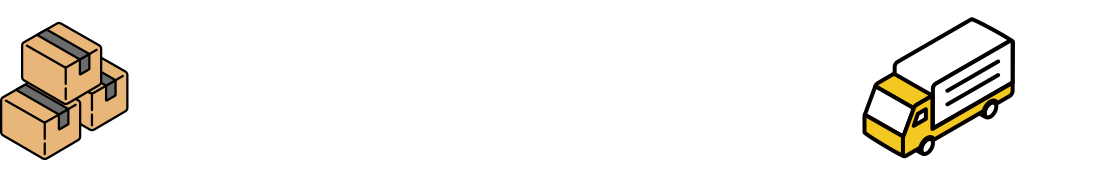高田泰(政治ジャーナリスト)の記事
高田泰(政治ジャーナリスト)の新着記事
-
水素発電の普及の課題のひとつは発電時のコスト高で、経済産業省は水素の販売価格を今の約3分の1以下にする目標としています。グレー・ブルー・グリーンと3種類ある水素の中で、グリーン水素は製造工程で二酸化炭素を発生させません。2050年カーボンニュートラル目標に向けて、コスト削減対策は必須です。
-
水素は発熱量が炭素の約2.5倍あり、二酸化炭素を排出しないため、クリーンな次世代燃料のひとつとして注目されています。ただし水素を供給するためのインフラ整備に課題が多く、普及が遅れています。国内の現状とともに、インフラ整備の普及のための課題について解説します。
-
原油価格の高騰による燃料コストが上昇。漁業、運送、クリーニング業界、イチゴ園の経営にまでダメージを与えています。また、石油製品・食品などの値上げなどの物価の変動で、私たちの暮らしにも影響をもたらしています。
-
全国のレギュラーガソリン平均店頭価格が、11月22日時点で168.9円。石油、天然ガスなどのエネルギー調達価格の上昇が続いています。エネルギー調達価格は電気料金と連動しているため、電気の需要が増える冬を迎えるにあたって、電気料金の高騰も心配です。
-
ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)は、建物で消費するエネルギーを省エネと創エネによってゼロ以下にした建築物です。カーボンニュートラル実現の取り組みのひとつとして推進されており、建設数が増加傾向にあります。各地でのZEBをいくつか紹介しつつ、ZEBの定義や動向について解説しています。
-
2050年のカーボンニュートラルへの取り組みのひとつとして、近年、グリーンボンド(環境債)の発行額の増加傾向が見られます。グリーンボンドは環境対策を目的とする資金調達のために発行される債権です。初めて市区町村レベルで発行した川崎市を紹介しつつ、グリーンボンドについて解説します。
-
仙台市ガスが民営化に向けて、2度目のガス事業譲渡先公募をしました。ただし、民営化によって利用者減となる企業グループの予測と譲渡価格に対して、仙台市は優先交渉権者の該当なしと判断。民営化を前提に再検討することとなりました。
-
マンションのZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化が、住宅選びの加価値として注目されてきています。ZEHマンションは、高断熱設計による省エネ性能の向上や太陽光発電や蓄電池などの導入によって、1次エネルギー(冷暖房・換気・給湯・照明)の消費量を削減します。今後新たな建築物の平均値となるZEH基準について、ZEHマンションの現状を紹介しながら解説します。
-
岡山県真庭市では、林業の不振による地域経済の回復を目的に、産業廃棄物となる間伐材などを活用して、木質バイオマス発電が始まっています。カーボンニュートラルへの取り組みとしてだけでなく、エネルギーの地産地消、雇用増加などさまざまな効果が期待されています。
-
合成燃料は、二酸化炭素と水素を合成して製造される新燃料で、人工的な原油ともいわれています。二酸化炭素の排出削減ができるため、2050年のカーボンニュートラルに向けて注目されています。