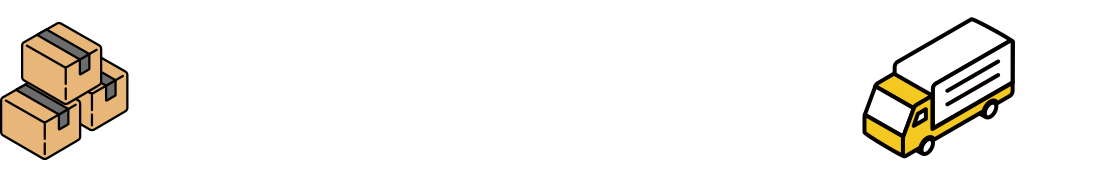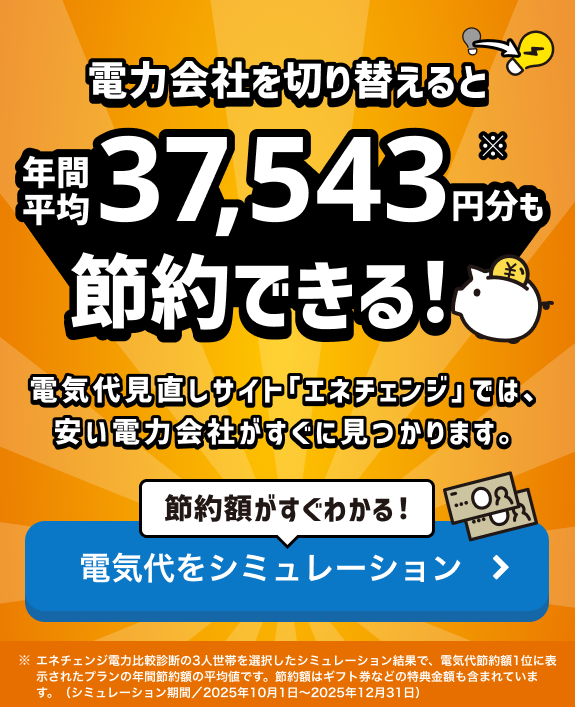再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)とは?2026年は値下げ?値上げ?

この記事の目次
毎月届く「電気ご使用量のお知らせ」(検針票)を見て、「再生可能エネルギー発電促進賦課金(はつでんそくしんふかきん)というのがかかっているみたいだけど、これって何?」と疑問に感じている方も少なくないはず。
再生可能エネルギー発電促進賦課金は通称「再エネ賦課金」と呼ばれ、私たち国民が負担することが決められているお金です。なぜ負担する必要があるのか、私たちにどんなメリットがあるのか、基本的な情報から解説しましょう。
- 更新日
- 2026年1月22日
再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)とは

再エネ賦課金は固定価格買取制度を支えるためのお金
世界各国は、地球温暖化の原因の1つとされているCO2の排出量を、2050年までに実質ゼロにする目標を掲げています。エネルギー起源のCO2排出量が世界で最も多いのは中華人民共和国、次いでアメリカ合衆国、インド、ロシア、そして日本が5番目につきます。
数字出典:世界のエネルギー起源CO2排出量(2020年)|環境省
CO2排出量削減の解決策のひとつとして挙げられているのが、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスといった「再生可能エネルギー」。再生可能エネルギーを利用した発電は、CO2がほとんど発生しない、発電に必要な資源が枯渇しないなどのメリットがある一方、コストがかかるという大きなデメリットがあります。このデメリットを解消するためにはじまった制度が、「固定価格買取制度(FIT制度)」です。
「固定価格買取制度」とは、再生可能エネルギーの発電所から作られた電気を電力会社が一定価格・一定期間で買い取ることを国が保証する制度。その電気の買取費用のために集められているのが、「再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)」なのです。
再エネ賦課金のメリット・デメリット
再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)を支払うことで電気の利用者にとってどんなメリットがあるのか、疑問を持つ方も少なくないでしょう。再エネ賦課金には大きく2つのメリットがあります。
1つは環境的なメリット。前述の通り、再エネ賦課金は再生可能エネルギーを利用した発電所の収益になります。収益がつけば、高コストな発電設備の費用回収の予測がつき、再生可能エネルギーの普及につながり、CO2排出量が減る、という流れが生まれるので、環境問題に貢献できることになります。
もう1つは、日本のエネルギー自給率問題の改善につながり、金銭的なメリットが得られる点。そもそも日本はエネルギー資源に乏しく、石油やLNG(液化天然ガス)などの化石燃料を海外から輸入してほとんどの電気を作っています。そのため、海外で化石燃料の価格が値上げされると、電気を作るコストも上がり、電気料金の値上げにつながってしまいます。再生可能エネルギーが普及すれば、化石燃料への依存も少なくなり、結果として電気料金の変動を抑えられると考えられています。
デメリットは、毎月の電気料金に含まれるため、家計の負担になってしまうことです。また再エネ賦課金単価は毎年見直しがされており、2022年までは値上げし続け、2023年の見直しで初めて値下げとなりました。
再エネ賦課金の計算方法
一般家庭の再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の計算方法は次の通りです。
- 再エネ賦課金=使用電力量✕再エネ賦課金単価
電気の使用量が増えれば増えるほど、再エネ賦課金が上がる仕組みになっています。
再エネ賦課金以外の項目も知っておきましょう
一般的な電気料金の内訳は次のようになっています。
- 基本料金(最低料金)+電力量料金±燃料費調整額+再エネ賦課金
上記に消費税が含まれます。
燃料費調整額は毎月見直しがされますが、再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)と同じく、私たち一般消費者の努力で値下げすることはできません。毎月の電気代を節約したいなら、現在契約中のプランよりも基本料金(最低料金)と電力量料金が安いプランに切り替える必要があります。
国内最大級の電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などを入力するだけで節約につながる電力会社を見つけられます。お得なキャンペーンを実施している電力会社も多いので、チェックしてみてくださいね。
平均37,543円/年の節約!
最安の電気料金プランを診断(無料)再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の動向

2026年は値上げ?値下げ?再エネ賦課金の単価推移
以下、再エネ賦課金単価の推移を表にまとめました。
| 期間 | 再エネ賦課金(単価) |
|---|---|
| 2025年5月分~2026年4月分 | 3.98円/kWh |
| 2024年5月分~2025年4月分 | 3.49円/kWh |
| 2023年5月分~2024年4月分 | 1.40円/kWh |
| 2022年5月分~2023年4月分 | 3.45円/kWh |
| 2021年5月分~2022年4月分 | 3.36円/kWh |
| 2020年5月分~2021年4月分 | 2.98円/kWh |
| 2019年5月分~2020年4月分 | 2.95円/kWh |
| 2018年5月分~2019年4月分 | 2.90円/kWh |
| 2017年5月分~2018年4月分 | 2.64円/kWh |
| 2016年5月分~2017年4月分 | 2.25円/kWh |
| 2015年5月分~2016年4月分 | 1.58円/kWh |
| 2014年5月分~2015年4月分 | 0.75円/kWh |
| 2013年4月分~2014年4月分 | 0.35円/kWh |
| 2012年8月分~2013年3月分 | 0.22円/kWh |
北海道電力・東北電力・東京電力EP・中部電力ミライズ・北陸電力・九州電力は「従量電灯B」、関西電力・中国電力・四国電力は「従量電灯A」、沖縄電力は「従量電灯」の再エネ賦課金単価です。
年度ごとに経済産業省が算定を行っていて、毎年5月に料金が改定されています。2025年度は3円98銭/kWhに決定し、2024年度と比較すると49銭/kWh値上げされました。
再エネ賦課金の値上げで、電気代はどれくらい高くなる?
「2025年5月分~2026年4月分」と「2024年5月分~2025年4月分」で毎月260kWhの電気を使用した場合の年間の再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)の差額を見ていきましょう。
- 2025年5月分~2026年4月分
- 3.98(円)✕260(kWh)✕12(月)=12,417円
- 2022年5月分~2023年4月分
- 3.49(円)✕260(kWh)✕12(月)=10,888円
再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、円未満を切り捨てた額になります。
電気の使用量が変わっていなくても、年間の負担額が1,529円も高くなっているのがわかりますね。
再エネ賦課金は毎年見直されるので、要チェック!
再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)が毎年見直されていること、再生可能エネルギーの普及に必要なことがわかりましたね。
再エネ賦課金の金額は国が定めたものなので安くできませんが、電力会社・電気料金プランを見直せば、電気代の節約につながります。電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、節約につながる電力会社を見つけられます。そのまま申し込みもできるので、ぜひ活用してみてくださいね。
平均37,543円/年の節約!
最安の電気料金プランを診断(無料)この記事を書いた人