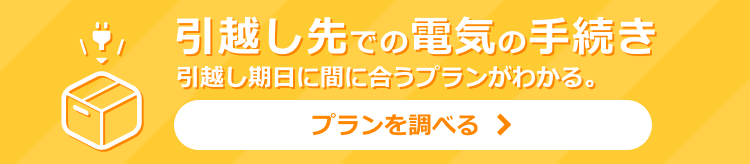いま原油が安い!原油価格の急落から家計の節約を考えましょう

この記事の目次
さまざまな食品が値上がりしている中で、皆さんもきっと「あれ、なんだかガソリン代が安くなっている?」と気づいているはず。そう、ここ数年一定の価格帯で変動していた原油価格が、昨年後半から急落しているのです。
原油価格の急落が私たちの生活にどのような影響をもたらすのか、また、今後の家計の節約のポイントは何か、一緒に考えてみたいと思います。
私たちの生活は原油に支えられています
原油はガソリンとして車を動かすだけでなく、電気を産みだし、ありとあらゆる物を作るために使われる貴重な原料です。日本は豊かな国ですが、唯一産出できないのが原油。私たちは国内消費量の99%以上の石油を外国からの輸入に頼っているのです。
だからこそ私たちの生活は、産油国や世界情勢、そして世界経済の動向の影響を受け安い!
私たちの生活を支える原油とは何か、ちょっとおさらいをしておきましょう。
原油は限りのある大事な資源です
原油とは油田から採掘したままの、精製されていない石油のことで、採掘した後にガスや水分、異物などを除去したものが原油と呼ばれています。原油は黒くて粘り気のあるドロドロした液体で、硫黄や酸素、窒素などの化合物も含まれてはいますが、その成分のほとんどは炭化水素の混合物が占めています。
原油は太古の海底に堆積した動物性プランクトンが化石化し、100万年もの長い年月の中で高温・高圧状態にさらされて化学変化してできたもの。
将来的には枯渇してしまう可能性のある、限りのある貴重な資源なのです。
2013年時の産出量の多い国と生産量は・・・
- 第1位 サウジアラビア 542,340(単位:千トン)
- 第2位 ロシア 531,434
- 第3位 アメリカ 446,231
- 第4位 中国 208,129
- 第5位 カナダ 193,013
- 第6位 イラン 166,082
- 第7位 アラブ首長国連邦 165,674
- 第8位 イラク 153,242
- 第9位 クウェート 151,253
- 第10位 メキシコ 141,846
原油は産油国によって成分の違いがあるのですが、日本で取引量が多いのはサウジアラビアが算出するアラビアン・ライトと呼ばれる原油です。
原油は古代から利用されています
原油の歴史は古く、紀元前3000年ごろのエジプトではミイラを作るときの防腐剤として、天然のアスファルト(原油に含まれる比重の最も重い成分)が用いられました。それ以外にも薬剤や建築物の詰め物、灯火としても古代から利用されてきたんですよ。
昔は油田を掘る技術はなかったので、地表に染み出してきた原油やアスファルトを採取して利用していたのですが、19世紀半ばに鯨油に代わって灯油がランプ油として利用されるようになって原油採掘の必要性が高まり、米国のドレークがペンシルベニア州に初の油井を建造して原油採取に成功したのをきっかけに、世界中で埋蔵量の調査が行われて大規模な採掘が始まっていったのです。
- 日本の原油の歴史
- 日本書紀には、越後国より天智天皇に「燃ゆる水」=原油が献上されたという記述があります。これは現代の新潟県胎内市で自然に地表に湧き出た原油であると考えられており、「臭水」とも呼ばれたそうです。
- 日本で原油がとれる場所は?
- 日本の油田は秋田県から新潟県にかけての日本海側に集中しています。現在では新潟県や秋田県の日本海沿岸、北海道の勇払平野などで原油が採掘されています。
- 日本産原油の消費量は?
- 国内油田の本格的な採掘は明治時代以降のことで、小規模な油田が秋田県や新潟県を中心に採掘をしていますが、国内消費量の1%未満の生産量しかありません。
原油はそのままでは使えない!?
私たちは産油国から原油を輸入してきますが、原油はそのままの状態で燃料として利用されることはありません。油田から採取されたままの原油には不純物が多く、成分のムラがありすぎて安定した燃焼とはならないのです。
そのために行われるのが精製という作業。精製によってさまざまな成分ごとに分離した石油製品は、それぞれの特性を生かした燃料として活用されます。
- 灯油
- 灯油は引火する温度が40℃以上と高いので常温保存がしやすく、家庭の暖房器具などに利用される身近な燃料です。純度を高めればロケットの燃料としても使えるんだそうですよ。
- 軽油
- 沸点が180℃から350℃の間にある燃料で、高出力で熱効率が良いため負荷の大きいバスやトラックなどのディーゼルエンジン車の燃料として使われるほか、引火・爆発の危険が低いため戦車などの軍用車輌にも利用されます。
- 重油
- 重油は原油からガソリンや灯油を分離した残りの燃料で、タール分などが多く、ネトッとした質感を持っています。ボイラーの燃料といった工業目的で使用されます。
- ガソリン
- ガソリンは沸点が30℃から220℃の間ととても低く、揮発性が高い液体で、私たちの身の回りにあるもっとも身近な燃料です。ガソリンは自動車用、航空用、工業用と用途別にさらに分類され、燃料や溶剤などに利用されています。
- ナフサ
- ナフサは沸点が低くガソリンとともに選り分けることができる液体で、燃料としての利用価値もありますが、大半はプラスチックなどの原料として利用されています。
原油から生まれる物にこそ価値がある!
原油はタダの燃料、なんて誤解をしていませんか?
確かに原油は生成されることによってガソリンや灯油などの性質の違う液体を作り出すことができますが、原油は石油製品という固体の原材料にも使われるのです。そして可燃性ガスもつくり出すことができるので、原油はまさに固体、液体、気体という物質の3態すべてに変化させることができる、万能な原料だといえますね。
- プラスチック
- プラスチックは石油製品の代表格。プラスチックが開発されるまでは木や竹やゴムなどの植物由来の素材か、金属の素材しかなかったのですが、プラスティックは加工がしやすく、安価な製品を作ることができます。
- 合成ゴム
- 天然ゴムは熱帯地方に自生するゴムノキの樹液を加工して作られますが、石油製品を加工することで天然ゴムと同じ性質を持つ人工樹脂、合成ゴムを作ることができます。
- アスファルト
- アスファルトは石器時代から黒曜石で作った鏃を矢に固定するために使用されてきた、なじみの深い石油製品です。重油から抽出されたアスファルトは道路舗装などに使われています。
- 化粧品
- 現代の化粧品の大半は、石油由来の成分で作られています。
- 液化石油ガス
- 私たちが料理やお風呂を沸かすときに使用するプロパンガスなども、原油から作られています。
原油の利用価値は高く、原油から調味料などの食品をつくる研究も進んでいるそうですよ。
原油価格の変動に興味をもちましょう
私たちが使う電気を作り出す火力発電所を動かしているのも、原油から生まれる石油製品。そう、原油価格の変動は電気代の値上がり・値下がりにまで大きな影響を与えているのです。
私たちの家計に与える影響が大きいからこそ、原油価格の動向をしっかり把握しておくことが、家計の節約の第一歩になるわけですね。
いま原油価格は一気に急落しています!
原油の高騰として記憶に新しいのが2008年の原油の高騰ですね。この時はガソリン価格は通常時の2倍近くまで値上がりし、車のガソリン代や燃料費などの家計を圧迫しただけでなく、石油依存度が高い運輸業や農業、水産業などが深刻な打撃をうけました。
その後リーマンショックの影響など影響で下落に転じ、ここ数年は1バレルあたり90~110ドルの間で原油価格が変動していたのですが、2014年後半から毎週連続して価格は下がり始め、価格が50ドルを割ることも!
ピーク時に比べて半値にまで価格が下がっているんです。
- 2012年 1月 113.37 (単位:ドル/バレル)
- 2012年 7月 102.26
- 2013年 1月 111.96 ⇐この辺は上昇と下降を繰り返していたのが・・・
- 2013年 7月 104.7
- 2014年 1月 113.51 ⇐ココから一気に急落!
- 2014年 7月 111.61
- 2014年10月 100.71
- 2014年12月 78.91
- 2015年 1月 63.36
- 2015年 2月 49.45
- 2015年 3月 54.73 ⇐ピーク時の半値にまで!!
価格急落の原因は?
2008年の原油価格の高騰には、産油国を巻き込む政情不安などに加えて、アメリカ経済のサブプライムローン問題が表面化したことをきっかけとした多額の投機マネーが原油先物市場に流れ込んだという背景がありました。
もちろん産油国を巻き込む戦争や政情不安などの影響も大きいのですが、原油は世界中で需要のある重要な商品であるだけに、さまざまな理由が重なり合うことで、原油価格は常に変動しています。
昨年から続く原油価格の急落にも、さまざまな要因があると考えられているんですよ。
- 世界的な景気低迷が影響している!?
- これまで製造業で業績を上げていたアメリカや中国の成長が伸び悩み、またヨーロッパ経済の低迷などが続いて、世界全体の景気が停滞しています。
不景気になると原油の需要が減ることから、需要アップのために原油価格が引き下げられたと考えられています。 - シェール革命が影響している!?
- これまで原油は中東を中心とした地域で産出されていましたが、最近になってシェール層と呼ばれる固い岩盤から原油=シェール・オイルを分離する技術が確立されました。
世界最大の原油消費国であるアメリカが、この「シェール革命」により自国内で原油生産を行えるようになり、アメリカの輸入量が大幅に減少したことが原油価格に影響を与えていると考えられています。 - 産油国が「シェール・オイル潰し」を画策している!?
- シェール・オイルの採掘には従来と比べて高額なコストがかかるので、原油価格が高値でないと利益がでません。
中東の産油国で構成するOPEC(石油輸出国機構)加盟国は、新興したシェール・オイルをコスト高で自滅させるために原油の減産をせず、価格を引き下げているという意地悪な見方もあります。 - 需要と供給のバランスが狂ったことが影響している!?
- 急激に経済発展を遂げている中国での需要に対応して増産した原油が、中国経済の伸び悩みにより余りはじめ、生産過多となっています。
余った原油を消費するため、価格が下がっているという考えがあります。 - 投資マネーの引き上げが影響をしている!?
- 原油は有望な投資商品。投資マネーが原油から引き上げられていることが価格の下落に大きな影響を与えていると指摘する人もいます。
今後の見通しは甘くない!?
今現在下降を続けている原油価格ですが、今後さらに原油価格が下がりつづけるのか、現在の低価格で安定するのか、はたまた高騰に転じるのか、いずれの方向に向かうかは不透明で、見通しがたっていません。
私たちの生活に大きな影響を及ぼす原油価格。今後も注意して、その変動を見守っていく必要があるようですね。
- 車社会が崩壊し、交通手段のほとんどが使えなくなる!
- 原油が購入できなくなると石油エネルギーで動いている自動車や飛行機、船舶などが動かなくなり、発電量も落ちることから電車も動かなくなります。
これは人間が移動できなくなるだけでなく、食料を配送する輸送機能が断絶することでもあります。 - 産業効率が低下して物を作れなくなる!
- 産業で使用されているエネルギーの大部分は石油によって供給されていますので、産業生産がストップして輸出品を作ることができず、輸入によって生産をあげることができなくなります。
- プラスチックなどの製品がなくなる!
- 、金属材料の加工にも石油エネルギーが必要になりますので、プラスチックの生産が出来なくなることで木材や竹を使った製品に立ち戻らざるをえません。
最近になってシェール・オイルの発掘ができるようになり事なきを得ていますが、このまま採掘を続けていけば原油がいずれ枯渇してしまうことは間違いないこと。原油がなくなってしまっても今の生活が維持できるようにするため、代替エネルギーの開発や人工的に石油を作る研究が進められています。
今後の家計節約のポイントは?
先行きが不透明だからこそ大事なのが、家計の節約。原油の価格が下がっていることのメリットを生かし、そのメリットをどう家計に生かしていくかが、腕の見せドコロですね!
原油も、そして原油から生み出される電気も限られた資源。エネルギーの未来を考えるように、私たちの家計の未来を考えていきましょう。
原油価格急落が家計に与える影響は無視できない
消費税率の改正、円安の影響と、ここ数年食品をはじめとする商品は値上がりをしています。物価が上がれば賃金もあがっていくのが望ましい経済ですが、円安が進んだ割には収益に結びつかず、私たちの賃金アップにはなかなか望めない状況が続いていました。
そこにきての原油価格の急落は、まるで社会全体で臨時のボーナスをもらったようなもの。景気回復につながる影響もではじめています。
- ガソリンや灯油の販売価格が下がる!
- 円安の状態だとあまり大きな価格差はありませんが、原油から生成されて作られるガソリンや灯油などの販売価格が下がります。
車でのお出かけや冬の暖房代の負担が減りますね。 - 生鮮食品や鮮魚価格が下がる!
- 野菜をビニールハウスで作る時、漁船で魚を獲るときにも燃料として石油製品が使われますので、生産コストが下がることで販売価格は下がることが期待されます。
- 消費が増えて好景気がやってくる!
- ガソリンをはじめとする石油製品や、間接的に影響を与える食品などの価格が下がることで消費が増え、好景気の引き金になることが期待されています。
- 賃金がアップする!
- 原油の値下がりにより、幅広い業界でコストダウンが図れ、生まれたゆとりが従業員の賃金アップに結び付くことが予想されています。
- 都市部よりも地方が元気になるかも!
- 自動車の保有率は都市部より地方の方が高いことから、原油安のメリットは地方にこそ効果があります。単なる物価上昇ではなかなか景気回復の効果が地方にはいきわたりませんが、原油安による景気回復で地方から元気になれるかもしれません。
原油安での家計節約のポイント
さてさて、それではこの原油安のもたらすメリットを、どう家計の節約に役立てていけばいいのでしょうか。
今回の原油安を考える時に大切なのは、今回の原油安がさまざまな要因が絡み合って先行きの見えない現象であることを十分理解しておくことです。
この原油安がいつまで続くのかはわからないこと。この状況に浮かれて「値下がりした!安い!!」と散財していくばかりでは、童話のキリギリスと同じ目にあってしまいます。
将来に備える節約のポイント!
- 無駄買いをしない
- 価格が下がると日本人は備蓄をしてしまいがちですが、急激に需要が増えれば逆に値上がりのきっかけを作ってしまいますので、値下がりした商品の必要以上の買い込みはしないようにしましょう。
自宅でも保管はできますが、灯油は温度や直射日光、空気による酸化などで劣化しやすい石油製品です。古い灯油を使うことでストーブが壊れたり、黒煙がでたりと事故になる可能性も高いので、ポリタンクでの保管はほどほどにしましょう。 - 浮いたお金は貯蓄にまわす
- 原油安によって景気回復が期待されていますが、将来のことは見通しがたちません。年金の減少など、将来使えるお金も減っているのが現状ですので、ガソリン代の値下がりによって浮いたお金や、賃金アップにより増えた収入は積極的に貯蓄にまわし、将来に備えていきましょう。
- 電力会社を賢く選ぶ
- 発電にも原油が使われるため、原油安を受けて電気代の値下げを始める電力会社もありますね。ただし、天然ガスを利用する火力発電所では円安により天然ガスの調達コストが上がっていることから、値上げ傾向にあります。つまり、自分たちの家庭で使う電気力会社を、賢く選ぶことが大切なんです。
景気の回復に浮かれて散財キリギリスよりも、もしかしたら来るかもしれない冬を乗り切る、節約アリを目指しましょう!
今回の節約ポイントにあるように、今後の家計を考えるうえで、「電気」はとっても重要なポイント。皆さんもエネチェンジ電力比較で電気代の見直しをして、賢く電力会社を選んでいきましょう!!